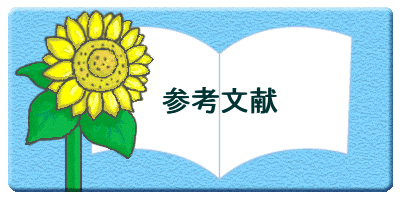
私のクーン『科学革命の構造』について、内井惣七氏から「訳が悪いから、勧められない」という評価をホームページに出されて、いつまでも消えないので、私も自分のホームページを立ち上げて、反論する。
要するに、私もまず直訳して、それから日本語として彫琢して行く。私が手を入れればいれるほど、努力すればするほど、直訳から離れていって、内井氏にいわせれば、訳が悪くなって行く。ところが私は逆に、直訳から離れれば離れるほど良い日本語であると思っている。これは原理的に反対方向を向いている評価法である。
今時、直訳は誰でも出来る。機械でも出来る。それを日本語として読みやすくするのが、訳者の日本人読者にたいするサービスだと私は思っている。私はクーンの所説は完全に理解しているので、その頭から発する私の言葉は、内容的に直訳から遠く離れていても、日本語としてもっとわかりやすいし、大筋から違うことはないはずである。
まさか直訳者は冠詞と単複まで訳そうとはしないだろうが、関係代名詞は日本語にない形だから極力避けるべきである。単文に切る方がよい。受け身も本来の日本語にないもので、形式的な翻訳にはやたらに出てくるが、やはりできれば能動態にすべきである。
さらにもっと微妙な点に触れると、直訳では、ついどこに重点があるかが見えにくくなる。それに、英語国民にとっては英語の単語の間にウエイトの差があることは読む者に自然と身についているのだが、それをそのまま日本語に直訳すると、どの言葉も同じウエイトになってあらわれ、ついのっぺらぼうで、わかりにくく、二度三度読み返さなければ意味が通じないことがある。それは直訳翻訳調だからである。また、なめらかな日本語にするために、時には口述にして語呂を整える労もとる。
翻訳する際にながく丁寧に訳することが無難であることはよくわかる。これが古典学の注釈なら、限られた専門家の間で一字一句を金科玉条として扱うのはわかる。しかし、クーンの意図はそんなところにない。頭をひねってわかったあげく、何だ、そんなことか、大したことを云っているのじゃあない、と気づいたときの空しさはだれしも経験していることだろう。私も、原直訳に手を入れるとき、とかく肝心なところを浮き彫りにするために、余計な細部を犠牲にすることもある。それはのっぺらぼうな文章を監修させられると、ついいらいらして、削りがちで、私の訳文も直訳よりはふつう短い。
中学の時、英文和訳が教師よりも出来た私は、直訳は当時すでに完成したものを持っていた。大学を出てはじめて翻訳を出版したときは、確かに直訳調であった。以後、翻訳は日本語として良くすることだ、と思って、直訳から離れるように心がけて、その完成は25歳の時に訳した3冊目の訳モリス・クライン『数学文化史』に見られる。そこには詩が多く含まれるが、詩などは直訳しても無意味・不適切である。
ただ、その過程で、この訳が中学生の虎の巻にでもつかわれたら、かなわんな、と思っていたが、今回はしなくもそういうことになって、苦笑している。たとえば、私がfundamentalを「重要な」としたからと言って、批判者はfundamentalのふつうの訳語を私が知らないとは考えないでください。辞書に出ていない訳語は誤訳だというのは、あまりにも中学生的です。クーンをテキストにして英語を勉強しょうというのなら、原文を読んでください。私には愚かな直訳主義に組みする気はない。
私は高等学校の時に、天野貞祐のカント訳に辟易し、明治の哲学字彙にあるような訳語は当時訳された専門語の訳のうち、権威主義的で最も趣味の悪いものだと思っているので、若い頃、哲学用語をふつうの言葉で置き換える運動を試みたものである。
この訳ではそこまで気負っていないが、たしかに訳するときに自分の意見がどこかに出ていることは否めない。たとえば、commensurabilityは哲学では気になる問題になろうが、科学者にとってはつまらない問題になる。そのまま直訳してはおもしろくないので、私ははじめ止揚性と訳した。しかし、それでは私の考えが出過ぎていると、後の版ではふつうの訳にした。
次に批判者はクーンの原文のどの版と対照されたのだろうか。私の訳したのは1962年の第1版であるが、それに対してクーンからしょっちゅう改訂を申し込まれ、さらにそれを取り消したり、前後撞着することがあったり、当時彼は科学哲学者たちから総攻撃されて、彼の言葉を誤解されることを恐れて、完全にノイローゼ状態であった。だから私の訳したものは第1版と第2版の中間のものと思っている。ただ、当時出版社がこの仕事の意義に気が付かず、それに原稿紛失の事故もあったりして、出版が第2版よりも遅くなった。
さらにそれよりもより深いところに、内井氏の批判の背後に、クーンに対する、あるいは私に対する批判があるのではないだろうか。それはクーンがノイローゼになった初期の批判に似ているところもあるので、ここで触れてみたい。
クーンが相対主義者だという非難がある。それが伝統的科学哲学を破壊したということらしいが、彼にも私にも相対主義者であることがいけないことかどうか、さっぱりわからない。人は絶対主義者でなくてはならないらしい。
私も1955年ハーバードに行ったとき、科学哲学の講義に出たが、一言で云えば失望であった。マッカーシーパージからの逃避所であったのか、symbolic logicに矮小化していた。またその後もBoston Studies in Philosophy of Scienceの月例会合に出て、つき合ってみた。これらのつきあいでは、相変わらず古い議論をしている。私もついその気になって討論に参加するが、その後昔と同じことを繰り返していっている、と言う失望感に伴われる。クーンが有名になって後は、その会はクーンを無視するか、論題にすれば、嘲笑することがふつうであった。Bob Cohenのような私の親しかった男もクーンはとりかえしのつかないダメージを与えた、と非難していた。
私は何も科学哲学を間違っている、と言うつもりは全然ない。ただ、つまらないのである。彼らは科学の哲学的問題が気になって、その中に入ったのであろうが、彼らの頭の中で構築した科学なるものは、現実に行われている科学とは関係ないものである。
クーンは第2版以後物理学史に帰って10年で本を書いた後、晩年はまた科学哲学者と付き合った。その時は、彼らも(Bob Cohenも含めて)クーンに合わせてより友好的になっていたが、クーンは科学哲学者の科学観を正すことに残りの人生を費やしたようだ。
山岡洋一氏の翻訳通信に、「クーンの『科学革命の構造』の翻訳に関する見解が出ています。